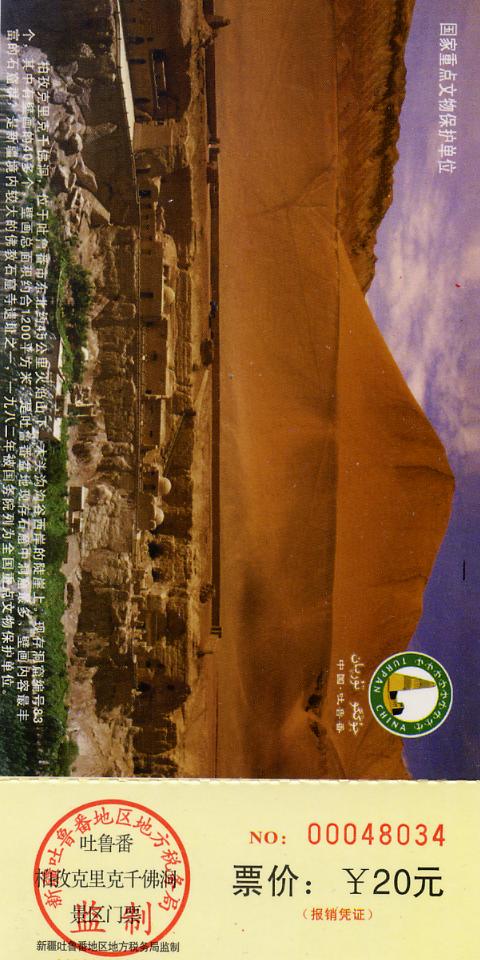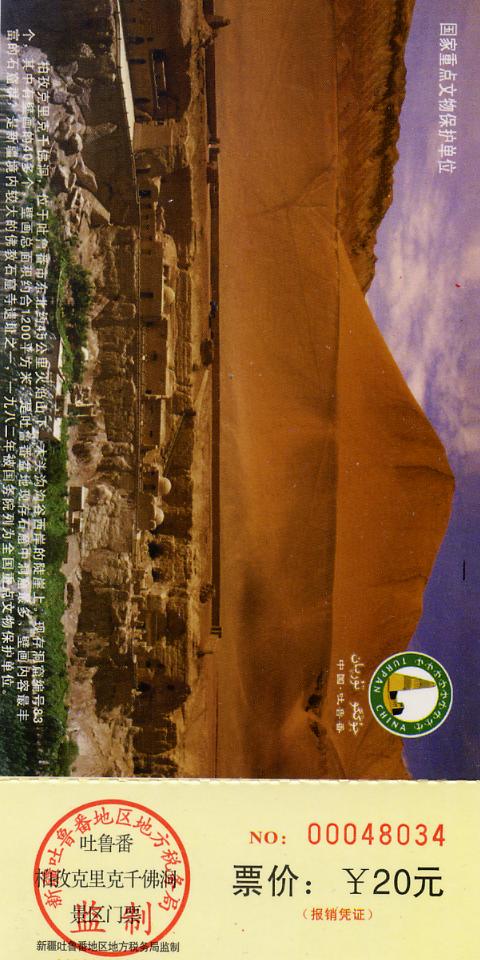炎天下の皆既日食・食事編
(19)カシュガル民謡との出会い
あまりに長時間同じ姿勢で座っていたので、非常にトイレが近くなりました。トイレは入場券を発券機に通して中に入らないと無いそうです。急いで中に入り、トイレの場所を聞いて用を足しました。ここは水洗トイレですが、自動では流れないので近くにあった水桶で水を汲んで流しました。トイレットペーパーもそのまま流すと詰まってしまうそうなので、別の場所に投げました。
火焔山と言っても平たく言うと遺跡巡りです。遺跡は階段を下ったところにありました。当然内部は撮影出来ないので、一眼レフで建物や自然などを撮りました。遺跡内部の玄関口に椅子が置いてあったので、ロクに説明も聞かず休んでいました。最後の遺跡に近づいた時、何やら聞き慣れない音楽が流れ出しました。
音楽の鳴っている方向へ行くと、そこには日陰の椅子に座っていたウィグル族の老人が弦楽器を持って弾いていました。その独特の高音域の音色に引き込まれた私は、ツアーの遺跡案内が終わってもなおビデオカメラで撮り続けていました。帰国後にその不思議な弦楽器を調べると、ラワプと呼ばれる弦楽器だそうです。
これは、木製の胴に蛇皮張りで全長が約1mもある大きなものです。楽器の胴は木をくりぬいて作ったものです。演奏者は胸高に水平に構え、左手で弦を押さえて右手に撥を持ち弾奏します。主に民族舞踊や歌の伴奏に用いられています。
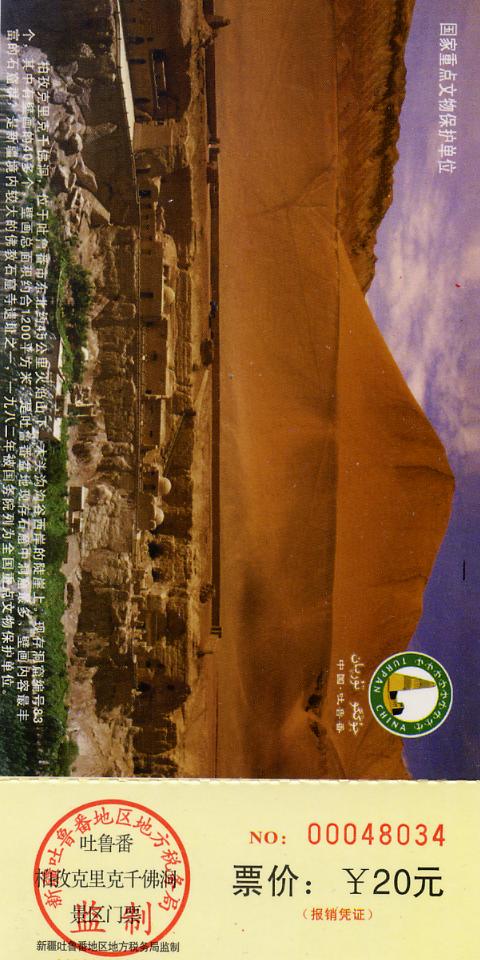 火焔山入場券
火焔山入場券
音を聞いて戴ければ分かるのですが、非常に速いテンポの曲です。これしか演奏の題名が分からなかったので、カシュガル民謡をupしてみました。これで三味線を弾けたら迷わず楽器を手に取って弾いてみたのですが
。隣にもう一人ウィグル人がいてタンバリンのような太鼓を持って叩いています。これら音楽を総称してムカムと言います。歌も韻やリズムが多種多様にあります。歌詞は不明ですが、詞やことわざ、庶民的な人生観などが多く書かれているそうです。まさにムカムは、ウィグル社会の縮図と言えるのではないでしょうか?
後日、別のバザールでラワブを買える機会がありました。これは蛇の革が張ってあると言うことで、中国国外に持ち出しすることは禁止だそうです。
最初はシレッとしたあまり元気なさそうな顔でラワブを弾いていたのですが、ツアー客が集まって奏者の足元に元を置くと、弦を引く音が明らかに大きくなったのが印象的でした。この奏者は足が不自由そうで、一日中日陰でツアー客を相手に弾いているそうです。一番最初に入ったトイレのある建物が土産物屋です。そこもツアー客が集まっていました。ガイドの胡さんに手招きされて行ってみると、冷風機が置いてありました。迷わず冷風機の前に立って涼みます。反対側の出口付近にはウィグル族がかぶるような帽子が売っていました。
 民謡を弾いているウィグル人
民謡を弾いているウィグル人
次へ